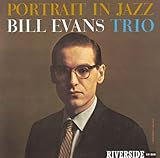保坂和志と高橋源一郎そして笙野頼子氏等に端を発した『小説は小説家にしかわからない』事件って『事件』なのかどうかは別としてなんか色々とネットをヲチしてたんだが私から見ると「論争」といえるものなのかどうか分からない。一種の文壇政治ゴシップみたいに思うのは不遜であるかも知れないが見え隠れする作家という矜持に違和感みたいなものを持ってしまった。いわゆる作家先生の鼻持ちならなさみたいなものに不快の念を禁じ得なかった、と云う風に言ってもいいだろう。しかし今となれば記憶の隅っこに移動してしまっていて当初感じた苛立ちは消えてしまっている。
保坂和志と高橋源一郎そして笙野頼子氏等に端を発した『小説は小説家にしかわからない』事件って『事件』なのかどうかは別としてなんか色々とネットをヲチしてたんだが私から見ると「論争」といえるものなのかどうか分からない。一種の文壇政治ゴシップみたいに思うのは不遜であるかも知れないが見え隠れする作家という矜持に違和感みたいなものを持ってしまった。いわゆる作家先生の鼻持ちならなさみたいなものに不快の念を禁じ得なかった、と云う風に言ってもいいだろう。しかし今となれば記憶の隅っこに移動してしまっていて当初感じた苛立ちは消えてしまっている。しかし、最高の批評は作品からおもいがけないものをつくりだす創造作業だ。作品に価値を与えることができる。作品を鐘になぞらえてハイデガーがそういっている(とブランショがいっている)。批評はその鐘を打つ打ち方で、だれも聴いたことのない響きをつくりだせたとき、その批評は最高の批評なのだ、と。しかも、その批評のあと、その響きは、はじめから鐘が持っていたものだとされる。作品を輝かせると、そのときにはもう批評は消え去る。触媒に、「消える媒介者」にすぎないものとなる。その消滅こそが、批評のほこりなのだ、と。
-「欲望なんてものはない」-坂のある非風景-
批評が批評たりえるのはM氏がいうとおり作品の雰囲気を批評家たるものがどう伝えることが出来るのかでしかない。そしてその点で批評も文学という範疇に棲息出来うるものだと思っている。そして批判も批評のひとつでもあることは自明である。また世に棲む作家と呼ばれる人たちと批評家と呼ばれる人たちのせめぎ合いも有りとしなければならないだろう。読者というものが存在する限り「批評」と呼ばれるものも存在するのだ。レヴィナスは読み手となっている人たちを「受容者」と呼んでいて『現実とその影-Emmanuel Lévinas1948年』のなかで批評の本質を以下のように述べている。
マラルメを解釈することは、マラルメを裏切ることではなかろうか。マラルメを忠実に解釈することは、マラルメを抹殺することではなかろうか。マラルメが曖昧に語ったことを明晰に語ること、それは、マラルメの曖昧な語りの無効性を明かすことではなかろうか。
文学の営みとは区別された機能としての批評、専門的で職業的な批評は、新聞や雑誌の文芸欄や書物として登場するのだが、そうした批評がうさんくさいもの、存在理由なきものと映るということも、もちろんありうるだろう。
けれども、批評の源泉は聴衆や観衆や読者の精神のうちにある。こうした受容者たちの振る舞いそのものとしての批評が存在するのだ。美的喜びに溺れることで満足することなく、受容者は、語らなくてはならないという抗しがたい欲求を感じる。
芸術家が作品について当の作品以外のことを語るのを拒む場合にも、受容者の側には語るべきことがあるということ、-黙って観照することはできないということ-、それが批評家の存在理由である。
批評家をこう定義することが出来る。批評家とは、すべてが語られてしまったときにも依然として語るべき何かを有している人間であり、作品について作品以外のことを語りうる人間である、と。
-【芸術と批評-p303】(『現実とその影-Emmanuel Lévinas1948年』合田正人 訳)-
そして断固それは芸術家が蝿を払うようにしてもそれとして存在する。
※このエントリィは「愚民の唄」2007-12-23に書かれたものを転載した。
| レヴィナス・コレクション (ちくま学芸文庫―20世紀クラシックス) Emmanuel L´evinas 合田 正人 筑摩書房 1999-05 売り上げランキング : 49771 Amazonで詳しく見る by G-Tools |